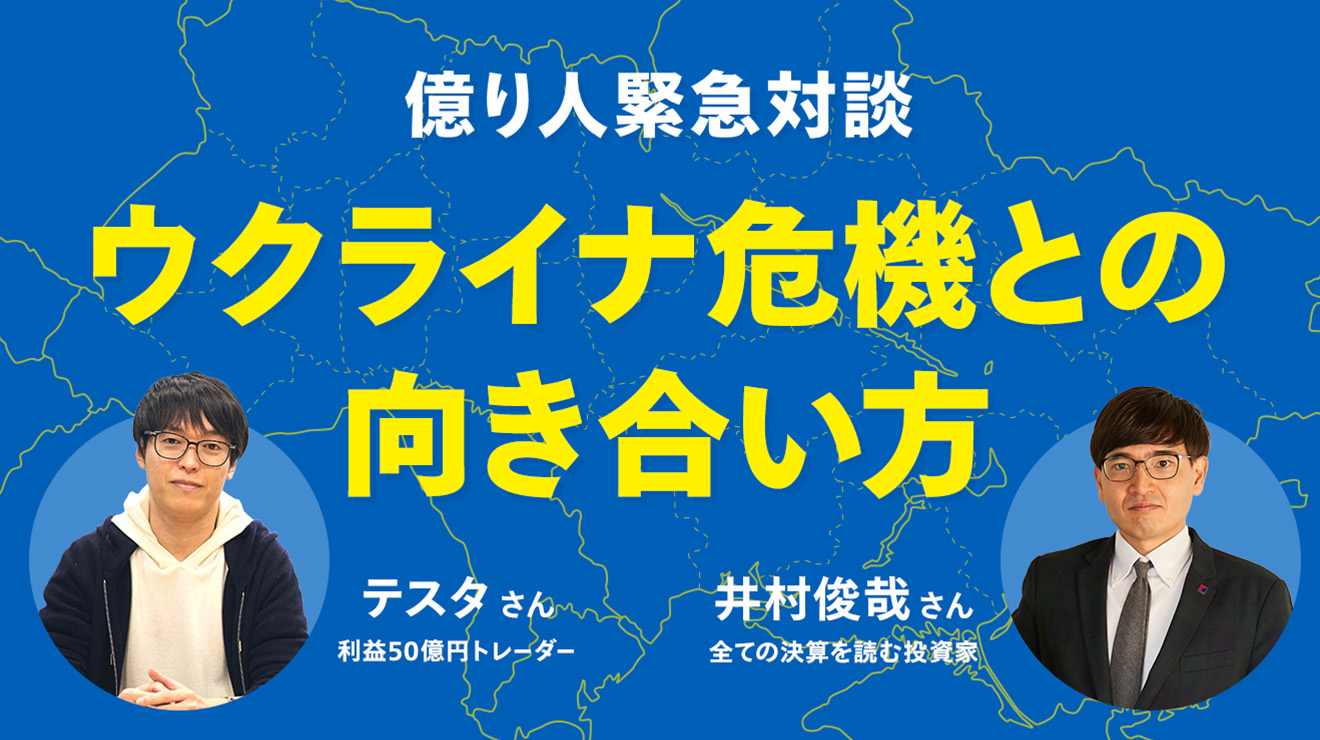ウクライナで起きてしまったロシアによる侵攻は、私たちの心を揺るがすと同時に、金融市場へも大きな影響を与えています。日経平均は一時、2万5000円を割り込むほどに下落しました。そんななか個人投資家は何を思い、どう行動したのでしょうか。難しいテーマでしたが、今回ご協力いただけたのは2人の億り人。決算などのファンダメンタルズから投資する井村俊哉さんと、値動きをもとにトレードするテクニカル派のテスタさんです。
この状況下で投資家は何を考えるのか
![]()
ロシアがウクライナへ侵攻し、大変痛ましい事態となっています。
![]()
現代でも戦争が起きてしまう。とても悲しいですね。
![]()
海外メディアの記事を読んでいると、目を背けたくなる報道も多く心が痛みます。
![]()
株式市場が大きく動いているので対応しないといけないものの、ウクライナが危機にある中、「投資をしている場合だろうか?」と感じています……。
![]()
僕たち専業投資家は投資を仕事とする以上、相場が動いたらポジションを解消するなり、投資先を変更する必要があります。ですので、本業である投資とウクライナ支援は分けて考えています。ウクライナ支援のためにできることは寄付などになると思いますが、自分にできることを考えて実行していきたいと思っています。
![]()
なるほど……! では、まず「投資」の部分について詳しくお伺いできますか?
![]()
新型コロナウイルスがまん延することでAmazonやウーバー、「出前館」のように売上が増えた企業がありました。でも、だからといって経営者や投資家は「コロナが流行ったほうがいい」とは思っていません。戦争についても同様です。それを大前提として考えれば、「今、投資していいのだろうか?」と考える必要はないんじゃないかと。
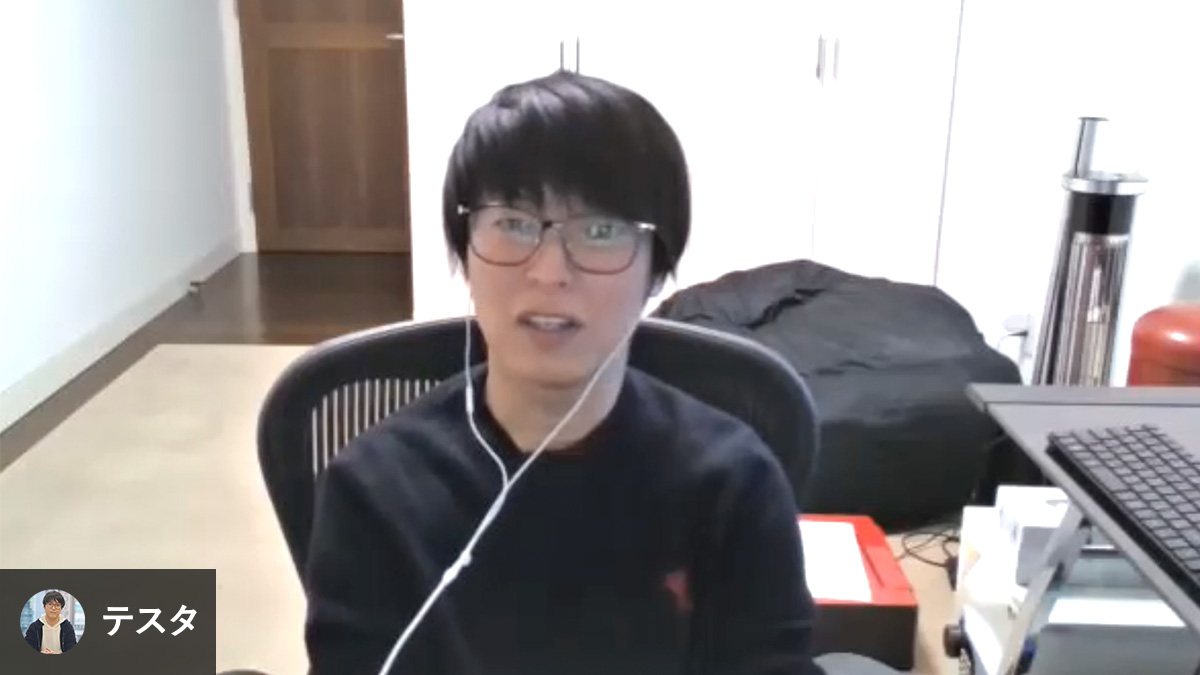
![]()
マーケットには、「社会が求めているもの」を示す「道しるべ」の機能があると思ってます。東日本大震災はとても悲しい出来事でしたが、復興需要によって建設株に資金が集まり、震災への備えも強化されて社会に足りなかった部分が補完されていきました。今回でいえば、原油や天然ガスなどが高騰し、エネルギー危機が起きています。危機を乗り越えるためにも、資源・エネルギーが必要だ、というマーケットのメッセージに耳を貸すべきだと思います。
![]()
原油などの化石燃料は、世界が脱炭素社会の実現に向かう中で人気が落ちていました。
![]()
脱炭素を叫ぶほど資源価格が上がってしまうというジレンマを危惧しています。なぜなら、世界的にエネルギー需要が高まっているのに、忌避されると供給を増やせなくなるからです。天候に依存せずに出力を調整できる火力発電の価値を再定義し、資源価格を下げるためにも速やかに増産する。それがエネルギー危機の解決に繋がると考えます。
![]()
戦争が起きないことを強く願いますが、先ほど申し上げたように、僕たち専業投資家は投資するのが仕事です。戦争で破たんする会社を買うのは投資家としては正解ではないし、ショック相場では投資した際の前提条件が変わっているのだから損失を回避するためにも投資先を見直す。それが投資家として然るべき行動だとも思います。
昼夜問わず錯綜する情報に「もう11月の気分」
![]()
おふたりとも冷静に相場を見ていらっしゃるんですね。ウクライナ危機の前後でどのような売買をされていたんですか?
![]()
ロシアが侵攻する以前から日経平均が弱かったので買いポジションをそこまで持っていませんでした。もともとリスクヘッジで持っていた先物の売りを、さらに弱くなる出来事が起きたので増やした感じです。
「リスクヘッジ」とは、起こりうるリスクを予測して、対応できる体制を取って備えること。また、「先物取引」とは、将来のある日(決済期日)に、現在約束した価格で商品を売買できる取引のこと。こうした先物の特性を活かして、相場の下落に備えて先物を売る手法があります。
![]()
僕は、今こそ世界が求めるエネルギーを供給できる企業の出番だと思い、資源関連の銘柄を買い増ししました。
![]()
僕は海運関連の銘柄を持っていましたが、ウクライナ危機があっても上がっていたのでそのまま継続し、損切りすべき銘柄は損切りしてという感じです。
![]()
特別なことはせずに、日ごろからの投資行動を継続したということですね。
![]()
戦争がどうなるか、特別な情報を持っているわけではないし、そもそも誰にもわからないので。
![]()
己のやり方を初志貫徹するという意味では僕も同じです。ただ、今年はまだ3月なのに自分の感覚ですと11月くらいに感じています。
![]()
3月なのに11月……? どういうことですか?
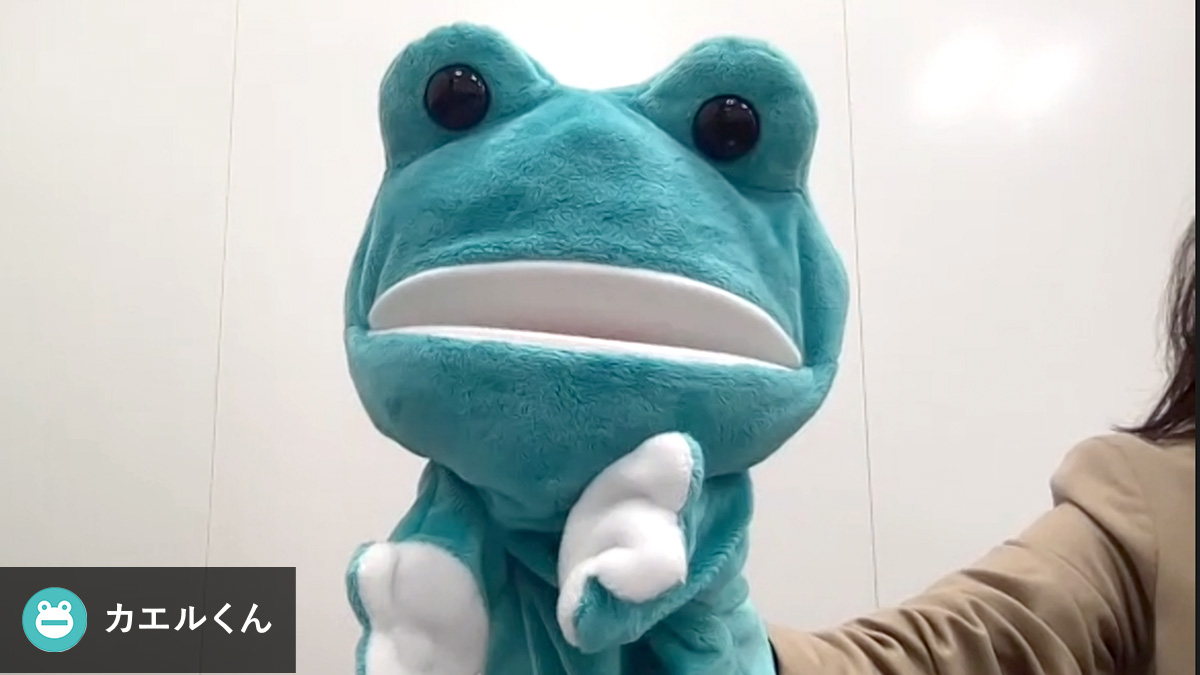
![]()
昼夜問わずニュースが飛び交い、毎晩寝る前は頭がパンパンです。ウクライナの戦線、欧米の制裁とロシアの報復、資源価格の動向、中国でのパンデミックにアメリカの金融政策、そして会社開示情報……ここまで外部環境がコロコロ変わる相場は珍しく、刻一刻とシナリオの調整を迫られています。
![]()
ただ日経平均を見ると2万8000円から2万5000円。2年前に起きたコロナショックは2万4000円が1万7000円になった。コロナショックに比べれば僕にとってはそこまでショックというわけではなかった。
![]()
海運など今の相場でも高値を保っている銘柄もあるので、チャートがいい銘柄を選択できているからかもしれませんね。マザーズ指数はコロナのときより悲惨ですよ。
![]()
井村くんはファンダメンタルズを分析して「これは減収につながるから売りだ」って判断していくんだろうけど、僕にはそれができない。株価が下がったらマイナスなファンダメンタルズなんだろうから売るし、上がってるなら持っておくし、その2パターンしかないから。
![]()
決算を徹底的に読み込む井村さんとは対照的なスタンスですね。
![]()
井村くんは毎日毎晩ファンダメンタルズを調べているけど、僕はファンダメンタルズをあえて見ない。というか、株価を見ていればわかる。株価が急激に上がれば戦争が収まるようなニュースが出たとわかるし、落ちれば悪化している。僕も井村くんみたいなやり方をめざして数年やってみたんですが、向いていないんでやめました。
![]()
逆に、テスタさんのように相場の空気を読みながらチャートについていくやり方は僕にはできませんでした。なので、誰よりもファンダメンタルズを調べ上げ、まだ見ぬチャートが右肩上がりになり得る銘柄を先取りするようにしています。この辺りは流派というか、向き不向きですよね。
億り人に聞く「暴落時の対処法」
![]()
今回のウクライナ危機でパニックになってしまった人もいるかと思います。とくに株を始めたばかりだと慌てて売ったり買ったり右往左往してしまいやすいですよね。おふたりは過去、暴落局面にも冷静に対応できましたか?
![]()
印象に残っているのはライブドア・ショック(2006年)とリーマン・ショック(2008年)ですね。ライブドア・ショックは僕が初めて経験したショックで、一番衝撃が大きかった。何度も経験していれば冷静になれますが、経験がないとパニックになりやすい。
![]()
テスタさんほどの投資家でも最初は大きな衝撃だったんですね……。
![]()
当時は値幅制限が今より厳しかったので、ストップ安になりやすかった。リーマン・ショックで主要銘柄がすべてストップ安に張りついた光景は未だに忘れられない。あの経験があったから今回の下げも冷静に見られます。
「値幅制限」とは、1日で変動できる株価の上下限を制限したもの。2020年に制限値幅の拡大要件が緩和されました。
![]()
ストップ安って身動きが取れない。やりようがないから怖いんですよね。
![]()
今は自分の資金が増えて売買するのが大型株中心でストップ安になりにくいし、少々のことでは揺るがずにできているんじゃないかと思いますけど。
![]()
僕は東日本大震災ですね。株で食っていこうと決意して早々、あの地震が起きました。午後2時46分でしたよね。木造アパートが激しく揺れる最中にもチャートから目を離しませんでした。妻が福島出身なんです。場が引けてから、連絡が取れなくなった妻の職場にダッシュしたことを覚えています。
![]()
ショックへの対処法はありますか?
![]()
ショックのとき初心者で多いのは、パニックになり、どうしていいかわからず塩漬けにするか、信用取引をしていたら追証が来て投げてしまうか。そうならないためにどうしたらいいかっていうのが大事で。
![]()
すごく心当たりがあります……。どうしたらいいのでしょうか?
![]()
結局、含み損が一定の額になったら投げるしかない。上がると思って買った株が下がったら、その時点で想定から外れている。想定から外れた株が上がっても、それは運でしかない。それが成功体験になって、次も同じことをやろうとしてしまう。大事なのは「再現性のある勝ち方」なんです。
![]()
自分はテスタさんと考え方が少し違っていて、マーケットは頻繁に間違えると思っています。僕が投資している資源関連株も含み損になったタイミングが何度かありました。特に今回のような大きな事象では、何が起きるか予想できないため、マーケットが織り込みを間違えることもあります。だから、ファンダ分析を徹底すれば、みんなが織り込む前に先回りできる。

○○ショックが起きたらノーポジに
![]()
ショックのときは底値を当てようとする人も多いんですが、それはやめたほうがいい。
![]()
たしかに「今日が大底だろうから買ってみよう」なんて考えてしまいがちです。
![]()
そうやってドンピシャで当てるとむちゃくちゃ気持ちいいし、利幅も大きい。でも、○○ショックなんて数年に1度しかない。そこで勝つより普段の相場で勝つほうがよっぽど大事。
![]()
ムリに大底を当てようとしなくていいんですね。
![]()
もしも、大底を当てられても偶然であることが多くて。例えば、急転直下で今、戦争が終われば株価は上がるんでしょうけど、それを「この日」と予想するのは運みたいなものでまず不可能。仮に当てたとしてもそれって再現性ないですよね。繰り返しになりますが、「再現性のある勝ち方」をしないと次につながらない。それに、底値だと思って買っても下落が止まらず大きく負けるとかもよくある。兼業投資家の人は、ショック時に攻める必要はないし、大きな下落相場のときは普通の相場に復帰するまで待っていたほうが生き残れる確率は高い。
![]()
なるほど……!
![]()
とにかく「喰らわない、損をしない、負けを最小限に抑える」をしみつかせるべきです。〇〇ショックが起きたらノーポジにして普通の相場になるまで待っていればいい。

![]()
テスタさんの教え、3箇条にして机に貼っておきます!
・普段の相場で勝つことを優先する
・○○ショックでは守りに徹する
![]()
「普通の相場に戻ってきた」というシグナルは何をみたらいいでしょうか?
![]()
普段、何を見て考える人なのか、によりますね。配当で考えるなら配当利回りが●%に下がったらとか、値動きなら底値から●%反発したらとか、それを前提にして崩れたら必ず損切りすることを徹底する。
![]()
自分の見解としては、この下落はアメリカの金融政策の大転換も深く絡んでいるので、当面は厳しい相場が続くかもしれないと思ってます。これまでのショックなら金融緩和や財政出動で株価を支えてくれましたが、今はインフレを抑えるために引き締めざるを得ず政府・中銀の支えが期待しにくい。そもそもウクライナ侵攻の前から、サプライチェーンの乱れを一因とした構造的なインフレは進行していて、ここにきて地政学的リスクで輪をかけてこじれてしまいました。これらは、需要の高まりではなく供給制約からくるインフレですので、リセッション(景気後退)入りをこれまでになく警戒しています。景気低迷で売上減、原価上昇などで業績が悪化してくる企業が増えてくるかもしれません。
暴落時の2つの鉄則
![]()
なるほど、井村さんはファンダ分析の結果、そのように見ていらっしゃるのですね。今のような暴落局面でのポジションの持ち方についてはいかがでしょうか?
![]()
ムリしてポジションを取らなくてもいいというのはテスタさんに同意です。なんとなく買ってなんとなく損切りする結果になりかねませんから。ただ、僕はこういうときこそ、情報を取り続けることが大事だと思っています。先ほど申し上げたように、今回のような大きな事象だと何が起きるか、予想が難しいし、マーケットも頻繁に間違えます。だからこそファンダ分析を徹底すれば、誰もわかっていないことを解き明かして、マーケットの先を行ける。そこへの努力は再現性があるし、ノウハウが蓄積できるからです。
![]()
どのように立ち向かっていけばいいでしょうか?

![]()
暴落時の鉄則が2つあります。暴落時は味噌も糞も売られファンダが機能していないように感じてしまいます。ですが、勇気を持っていただきたいのが、100年に一度の恐慌と言われたリーマン・ショックでさえ、2008年を通して東証一部銘柄の約1割の株価は値上がりしています。値上がりしたのは、円高で輸入が有利になった小売・飲食業や、資源価格急落の恩恵があった電気ガスなど業績好調な銘柄です。
(2)相場の金と凧の糸は出し切るな
![]()
一時的に株価が暴落してもファンダでよみがえったんですね! これは勇気づけられます!
![]()
暴落の原因となっている事象が個別企業のファンダメンタルズにどう影響するのか、見極めることに集中する。そして、常に身動きがとれるよう相場の金は出し切らない。これには、何があっても対応できるように余力を残すという守りの意味もありますが、自分の中では、どこまでいっても買ってやる、という攻めの姿勢を崩さない意図も含めています。
![]()
今の相場でファンダメンタルズを好調に保てるのは、どんな銘柄なのでしょうか?
![]()
大きく3つの狙い目があると思ってます。銘柄に落とし込むならば、本命はやはり資源・エネルギー関連ではないでしょうか。
(2)円安メリット
(3)脱ロシア
![]()
井村さんが大量保有報告書を提出していた「三井松島HD」も資源関連のひとつですね。
![]()
資源関連の注意点は、権益を保有しているか、です。資源関連と思っていても、実は加工や精錬をしているだけというケースも多く、その場合は、調達コストや工場の操業費の上昇が利益を圧迫する可能性があります。収益構造を銘柄ごとに精査するのは難しいので、もうひとつの考え方としては資源価格が高騰しても影響が軽微な内需のサービス業も悪くない。ただ、こちらも注意点があって、金融引き締めにより、以前よりもフェアバリュー(適正価格)が低下していくのではと思っています。フェアバリューがPER30倍だった銘柄なら、利上げによる重力で25、20と低下していくのではないか、と。バリュエーションをより厳しく評価し、極めて割安感のある銘柄を探すことも必要です。
![]()
資源価格の影響を受けにくい内需セクターというと、医療やヘルスケア関連などが当てはまりますか?
![]()
基本的に、インフレ圧力がかかりにくいサービス業や、小売りなら国内で仕入れられ、かつ、資源価格高騰の影響を受けにくい、たとえばリユース銘柄とかでしょうか。僕は買えてはないですが、リユースは不景気でも需要が減りにくいとも言いますしね。
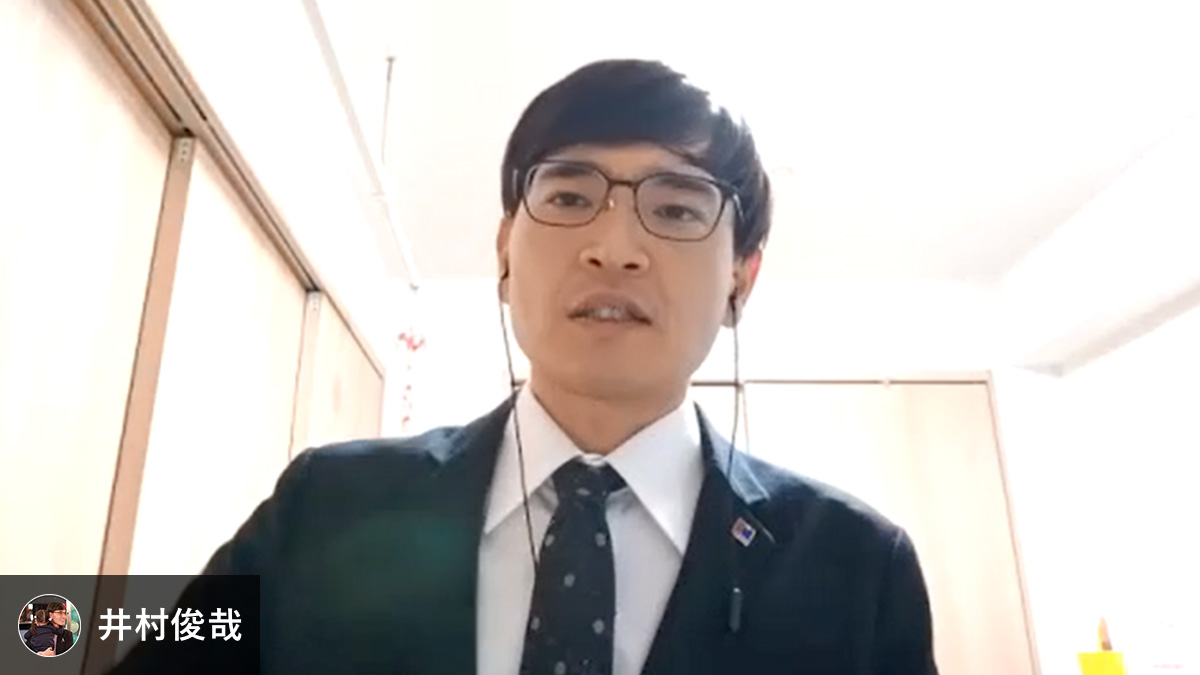
私たちが今できるのは「寄付と節電」
![]()
投資とウクライナ支援の話は分けて考える必要がある、と冒頭で教えていただきましたが、ウクライナの苦境を救うために今、私たちにできることはありますか?
![]()
単純に寄付だと思います。
![]()
僕は今できることは2つあると思っていて、ひとつは寄付。その際に気にしたいのが、寄付したお金の使途です。僕は食料や毛布など人道支援に使われる寄付先を選びました。もうひとつできることは節電です。
![]()
節電……?
![]()
なぜここまでロシアが強硬姿勢を取れるかというと、欧州向けの資源を人質にしているからです。ロシアからエネルギーを買う以外に電気を灯すことができない欧州は、戦争が激化する最中にもロシアの原油、ガス、石炭を購入し続けています。特に、ガスと石炭は4割強をロシアに依存し、それがロシアの活動資金になっています。日本も欧州ほどではないにしろロシアの資源に依存していて、戦争を少しでも早く終わらせるためにも電力の需要を減らす、節電することが大事なんです。
![]()
なるほど。節電をして電力需要を減らし、ロシア依存を断つことが大事なんですね。
![]()
電力不足は他人ごとではなく日本でも起きています。JEPXという日本の電力卸売市場の価格は高止まりしていますし、つい先日3月18日には、東京電力から電力需給が非常に厳しいとして節電の要請が出ていました。電力の使用率は98%にも上りあわや停電という事態。このままでは電気代の高騰含め、国民生活にも大きな影響が出てしまうという強い危機感を持っています。電力供給は急には増やせないので需要を減らすしかない。
![]()
原子力発電はどうなんですか?
![]()
原発には再稼働のスケジュールが細かく決められていて、それを変更するには政治的に大きな決断が必要。票が取れる政策ではないので夏の参院選を控えて現政権にその決断ができるとは思えません。憤りを感じますが……。
![]()
ロシアから石炭や天然ガスの供給が途絶えても、他国からは買えるの?
![]()
供給を増やせない以上、取り合いになります。大金を投じられる国は買え、貧しい新興国が割を食う。例えば、ミャンマーでは高くなったガスが買えなくなり停電が頻発するようになりました。
![]()
なんと……。ほかに供給が増やせる資源はないんでしょうか?
![]()
米国とイランによる核合意再生の協議で原油の供給が増える可能性はありますが、実は、石油火力が発電に占める割合は数%しかなく、電力需給を好転させるものにはなりにくい。アメリカのシェールガスは比較的早期に供給を増やせる可能性がありますが、ガスを液化するプラント、LNG運搬船、液化したガスを気化するプラントなど設備投資に数年単位の期間が必要です。再生可能エネルギーといっても簡単に増やせるものではないし、そもそも設備には金属シリコン、アルミニウムといった非鉄金属が必要で、これらは精錬時に大量の電気を消費します。世界が拙速に再エネ移行を進めれば、ただでさえ高騰している非鉄金属価格が一段高してしまう。石炭に関しては、脱ロシアへ世界に貢献できるとして豪州では増産に前向きな動きも出始めていますが、脱炭素に反するという世論を見るとこれも時間がかかる印象です。このように供給を増やすことは簡単ではなく、世界の秩序を守るために、僕たちが節電することはすごく大きな意味があるんです。ロシアが武器を買うお金も減らせるかもしれません。
![]()
寄付と節電が私たちに今、できることなんですね!
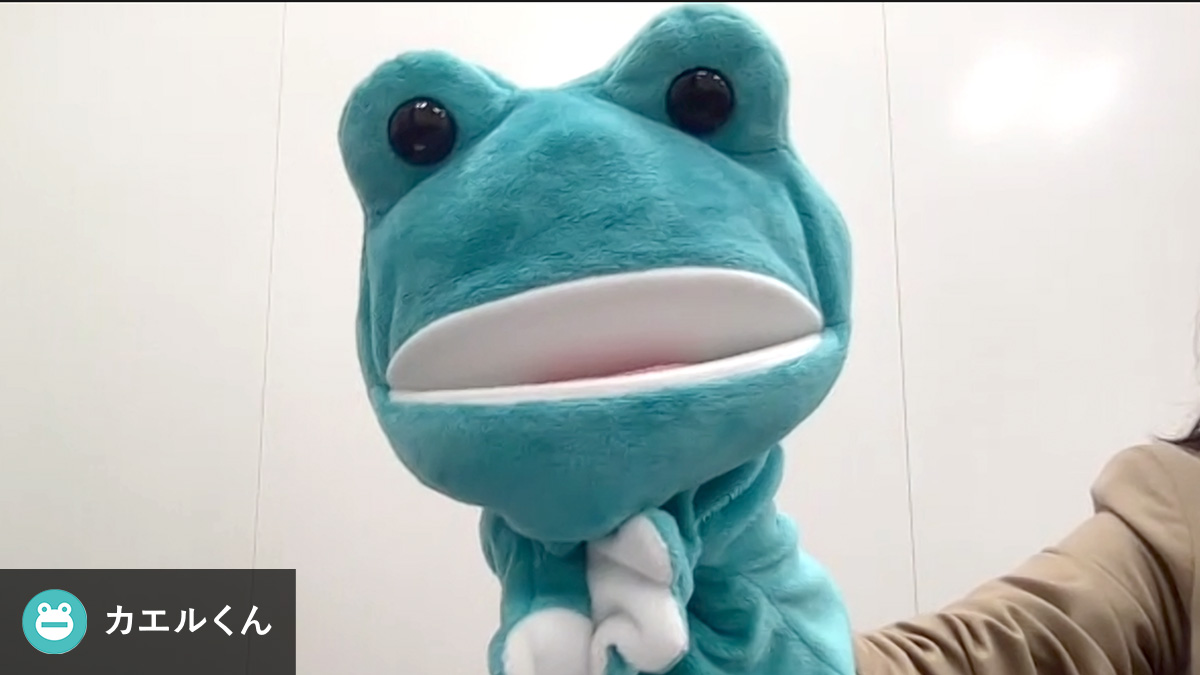
![]()
ここまでテスタさんと井村さんのお話を伺ってきましたが、タイプが本当に対照的ですね。
![]()
自分は膨大な情報から「業績はこうなるだろう」とストーリーを描いて入るんですけど、テスタさんはそれをチャートから察知して入る。結果として一緒になることもあって、僕は一銘柄100時間調べているのに、スマートに入られているテスタさんはなんだかずるいなと思うことも(笑)。テスタさんは、「相場の空気の読み方」が抜群にうまいんです。
テクニカルとファンダメンタルズの比率
![]()
テクニカル派とファンダメンタルズ派の違いはありますが、どっちも正解だと思うので、何を重視するのか、自分に当てはめながらやっていくといい。テクニカル派なのに井村くんみたいな考え方をしていてはよくないし、逆もそうだし。
![]()
僕らは95・5みたいに極端ですけど、そこまで極端じゃなくても50・50でもいいし、80・20でもいい、自分が心地いい塩梅を見つけてほしいですね。
![]()
はい! 自分に合った投資手法を見つけていきたいと思います。今日は難しいテーマだったかと思いますが、参考になる話がたくさんありました。ショック相場への対応、テクニカルとファンダメンタルズのバランス、ウクライナのために私たちができること――。ぜひまたおふたりのお考えを聞かせてください! 本日は、ありがとうございました。