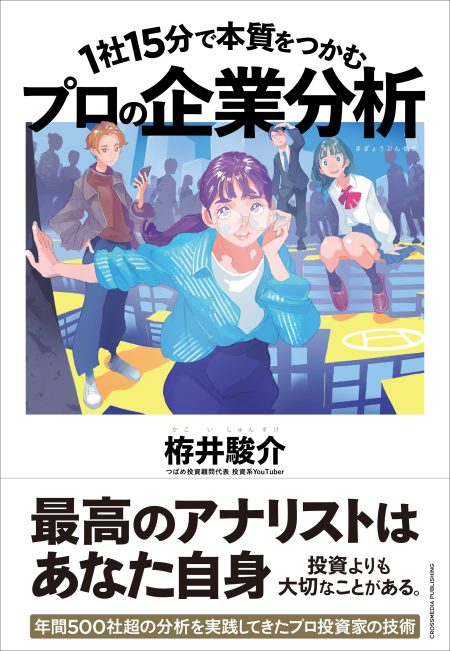投資や資産形成をもっと楽しくするためにピッタリの書籍を、著者の方とともにご紹介する本連載。今回は、資産運用における「基本中の基本のポイント」と「失敗する人の共通点」について、これまで延べ1,200人以上に資産運用アドバイスを行ってきた栫井駿介さんと見ていきましょう。[PR]
「よい企業」は、一人ひとりの中にある
ここまで数回の記事では、主に企業の分析方法を紹介してきましたが、そもそも何のために企業分析を行うのか、ここで改めて考えてみようと思います。
私が何を目的に企業を探すかと言えば、一義的には「投資先として、よい企業を探す」ためです。しかし、同じ投資でも、その考え方によって「よい企業」の定義が異なります。
私の場合は長期投資家ですから、基本的には「長期で業績を伸ばし続けられる」企業を探します。しかし、それだけでは十分ではありません。なぜなら、誰が見てもよい企業というのは、すでに株価が高いことが多いからです。
投資で平均以上の利益を上げるためには、株価が安い時に投資する必要があります。すなわち、まだ多くの人が気づいていないものに気がつく必要があるのです。「長期で業績を伸ばし続けられる」という条件に加えて「株価が高く評価されていない」「多くの人が気づいていない」ということを求めます。
そうやって考えた時に見るべきものは、「企業の変化」であったりするわけなのです。例えば、新しい社長が就任して、これまでとは大きな戦略の変化があった際に、これまでとは全く異なるストーリーが描けるのではないか。そのような観点で見るようにしています。
このようにして、自分の頭の中で描いたストーリーをもとに、投資先企業を決めます。その企業は、私にとっては素晴らしい企業かもしれませんが、このストーリーは私の頭の中にしかないので、他の人にとってはちんぷんかんぷんかもしれないのです。
私が企業を紹介する時にそのよさを話しても、相手からは全くと言って反応を得られないことも珍しくありません。同様に、私と同じような長期投資家の方と話をしても、そのよさが自分には伝わってこないこともあります。同じものを見ていたとしても、その先にあるストーリーの見方は大きく異なることもあるのです。
すなわち、企業の良し悪しは、それを見る人によって決まってくる、極めて相対的なものだということです。絶対的な答えなどなく、結局はその人にとっての良し悪しで判断するしかないのです。
これこそまさに、第1回の記事でもお話しした「推し活」に他ならないと考えます。アイドルのファン同士でも、自分の「推し」のよさを他の人に語ることはあれど、強要することはないでしょう。それぞれ違った意見があるからこそ、アイドルグループは盛り上がるとも言えます。
企業分析もこれと同じことが言えて、私から「この企業だけが素晴らしい」と言うつもりはありません。アナリストとして私に言えるのは、その企業にある客観的な事実までで、その企業をよいか悪いか判断するのは、その分析を見た皆さんに委ねられるのです。
長く付き合ってこその「推し」
長期投資を行う上で確かに言えるのは、「推し」がコロコロ変わっていくようでは成り立たないということです。長期投資で成果が出るためには、それこそ長い時間がかかります。成果が出る前に株を売ってしまったり、少し悪いニュースが出たからといって放り投げたりしていたら、一向に成果は得られません。
企業のよさを本当の意味で納得できていないと、長くその企業と付き合っていくことは難しいというのが、私がこれまで長期投資を実践してきた感覚です。
同じことは就職活動でも言えるのではないかと思います。数回の転職ならよいですが、何度も働き先を変えているようでは、スキルも信用も一向に身につかないでしょう。どこかのタイミングで、ここに骨を埋めるという「覚悟」が必要になります。
もっとも、最初から「この企業」と決めて長期で投資し続けたり、新卒で入った会社に何が何でも最後まで勤め上げたりするというのも合理的ではありません。物事の良し悪しを理解するためには、ある程度の経験値が必要です。
多くの企業に投資したり、就職したりするのは現実的に困難ですから、それを埋め合わせるものこそが企業分析であると考えます。様々な企業の分析をして、そこに投資や就職したかのような「疑似体験」を行い、自分が知っていることの幅を広げていく。それを続けることで、やがて自分の中で「好き・嫌い」が出てきます。
その感覚が身についてきたら、いったん企業分析の手を止め、「こんな企業に投資したい」というイメージを頭の中で思い浮かべたり、メモを書いてみたりするのです。
そのイメージをもとに再び企業分析に取り掛かると、今度は不思議と、その条件に当てはまる企業が浮かび上がってくるようになります。そして、やがて「運命」とも呼べる企業が目の前に現れるのです。これは冗談ではなく、数をこなしていれば、本当に訪れる瞬間があります。
これは「婚活」にも似ていると感じます。まず何人かの人と付き合ってみて、自分にとって「合う」「合わない」という感覚ができてくるのではないかと思います。すると、意識する・しないにかかわらず、こんな人と結婚したいという理想像がぼんやりと浮かび上がって来るはずです。そして、次に出会った人がそういう人だと感じられたら、まさにそれこそが「運命」だと言えるのではないでしょうか。
このように、企業との出合いも偶然性に左右されるものです。企業分析そのものは非常にロジカルでありながら、最後によい企業に巡り合うかどうかは、運に左右されるのです。ただし、その運を呼び寄せるためにも、様々な企業を分析し、自分の中にそれを受け入れる準備をしておくことが重要になります。
常に「ノートとペン」を持っておく
それでは、どのようにして「運命」の企業を探していけばよいでしょうか。
難しく考える必要はありません。なぜなら、よい企業はあなたの身近に眠っているからです。「こんな企業があったらいいな」と頭に思い浮かべておけば、無理にこちらから探しに行かなくても、企業の方から勝手にやってくるものです。
もちろん、ただ待っていればよいわけではありません。気になったとしても分析せずスルーしてしまったり、そもそもアンテナを張っていなかったりすれば、いつまで経っても見つかることはありません。だからこそ、私がおすすめするのは、「常にノートとペンを持っておきたい」ということです。気になった企業名だけでも書いておけば、後からその企業について分析するきっかけになります。
例えば、街で行列ができているのを見たとします。「これは何だろう?」と疑問を持った時点で、すでにあなたのアンテナに引っかかっているのです。「〇〇社、30人くらいの行列」とメモし、まずはその場で何のための行列か把握に努めます。そして家に帰ってから、あるいはその場でスマホでも構いません。有価証券報告書を見て、何をやっている会社か確認するのです。
もし直近の業績が上向き始めていたら、これから大きく成長するサインかもしれません。今日できていた行列のことは、まだニュース記事やアナリストレポートにもなっていないはずですから、あなたがその企業を分析する「第一人者」になれます。
アンテナに引っかかるということは、あなたはすでにその企業や業界の核心に迫りつつあるのかもしれません。もしそうなっていたら、「素晴らしい企業に出合う一歩手前」ということができるでしょう。